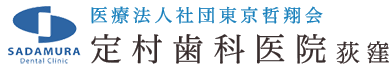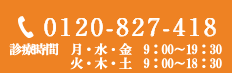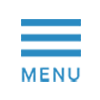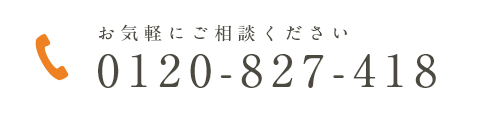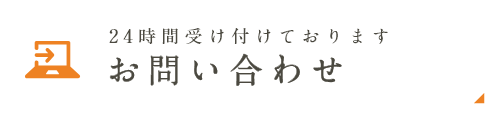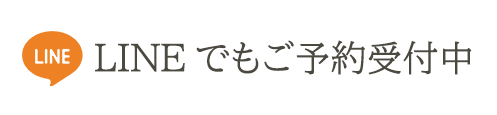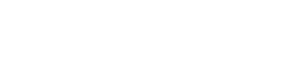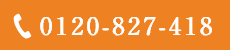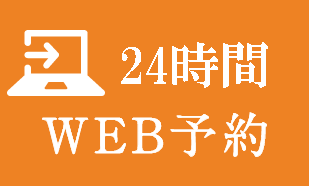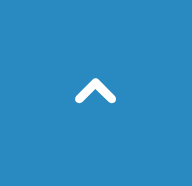季節の変わり目と歯や歯周組織のトラブルについて
杉並区荻窪の歯科医院 医療法人社団東京哲翔会 定村歯科医院 院長の定村正之です。
東京ではあっという間に桜の季節が過ぎ、新緑まぶしい爽やかな季節を迎えています。温かく過ごしやすい日もある一方で、急な天候の変化などもあり、体調管理には油断が出来ませんね。
さて、今回は抜歯後の歯を支えていた骨(歯槽骨)の形態変化について情報提供をさせていただきます。
矯正治療で便宜的に永久歯を抜歯する際や、かみ合わせに一切かかわらない親知らずを抜歯する場合を除き、抜歯になるケースでは何かしらかの歯のトラブル・歯周組織のトラブルが併発していることがほとんどです。
歯の周囲には通常歯根膜という薄い繊維組織があり、その周囲に歯槽骨といわれる歯を支える骨が存在しています。しかし、歯の周囲にトラブルが生じると、歯根膜がダメージを受け炎症を起こし、その流れで歯槽骨もダメージを受け、吸収(溶けてしまうというイメージ)してしまいます。
歯の周囲のトラブルには代表的なものとして以下の3つがあります。
① 歯周病:歯肉炎が進行し、歯周組織がダメージを受けた病態
② 根尖性歯周炎:歯の内部に感染が生じ、根の先を中心として根尖周囲組織がダメージを受けた病態
③ 歯の破折:歯にヒビや破折が生じ、ヒビや破折に沿って歯周組織がダメージを受けた病態
どの場合も、歯周組織(歯根膜や歯槽骨)にダメージがおよび、歯の保存が難しいレベルのトラブルの場合は、歯周組織のダメージもそれなりに拡大していることがほとんどです。
このようなケースでは、抜歯を丁寧に行うと同時に、抜いた歯の周囲の炎症組織をきちんと除去しないといけません。抜く歯の場所にもよるのですが、多くの場合は頬側・唇側の骨が大きく失われることになります。これは、解剖学的に頬側・唇側の骨の厚みがそもそも薄いという事に起因します(抜歯する前などで腫れるのも多くの場合、骨が薄い頬側・唇側で舌側が腫れることは稀です)。また、抜歯時期が遅れる場合や、口腔衛生状態が悪い場合には、炎症がいっそう拡大していることもあり、抜いた歯の周囲の骨欠損が大きくなってしまっていることもあります。
抜歯後に元通りに骨の穴が埋まればよいのですが、通常は歯槽骨もそのボリュームがダウンしてしまいます。
抜歯後にインプラントをする予定の場合や、審美エリアの場合には、骨の大きな欠損はのちの治療の難易度を上げることに繋がります。そのようなこともあり当医院では、抜歯時に抜歯窩を早期治癒させるためのコラーゲンによる組織回復や、粘膜治癒後に骨造成を施し、骨形態を改善する治療も行っております(一部健康保険外治療になります)。
抜歯は避けたい治療の一つになるかと思われますが、長い人生ですので、先々のことも視野に入れて最善の治療を選択することが重要であると考えています。抜歯したくないという気持ちもよくわかりますが、一定以上に状態が悪化してしまった歯は、残すことで周囲組織のダメージに繋がるので、時には早めの抜歯が正解になることもあります。症例ごとに、抜歯自体のリスク、抜歯をしない場合のリスク、抜歯後の治療法などを案内しておりますので、心配なことがあれば何でも確認してください。
では今月もどうぞよろしくお願いいたします!
医療法人社団東京哲翔会 定村歯科医院
理事長 定村正之